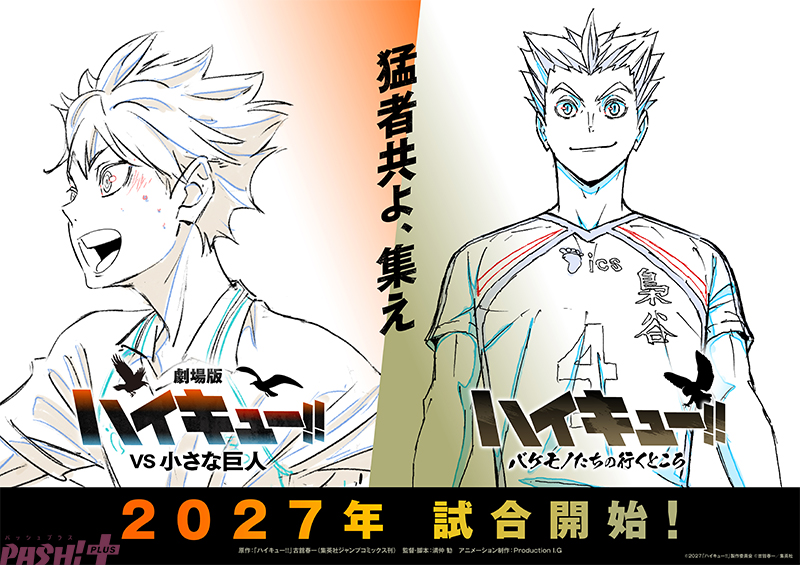anime
映画『ひるね姫』神山健治監督インタビュー
2017.03.17 <PASH! PLUS>
PASH! PLUS
神山健治「何も起こらない日常こそが、いちばんのファンタジーだと思ったんです」
2017年、いよいよ3月18日(土)に公開の『ひるね姫~知らないワタシの物語~』。
本作は、『攻殻機動隊S.A.C.』『精霊の守り人』『東のエデン』などで知られる神山健治監督が自ら脚本も手がけたオリジナル長編劇場アニメーションで、「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2017」のオープニング招待作品にも選ばれました。
2020年の東京オリンピック直前の岡山県・倉敷を舞台に、居眠りが得意な女子高生・ココネが見る夢を通して冒険と家族の絆を描いた本作。今回、公開を直前に控え、作品に込められた想いや製作秘話などを語っていただきました!
『ひるね姫』は逆『不思議の国のアリス』!?
――本作を制作された経緯として、奥田誠治プロデューサーから「自分の娘に観せたい映画を作ったらどうだろう?」と言われたのがきっかけと伺いました。また“夢”が大きなキーワードと伺っています。神山監督が実際に見た“夢”なども作品に投影されているのでしょうか?
“夢”そのものというより、自分の子どものころを振り返ると、その時期に観ていたアニメと現実がごっちゃになっていたときがあるんです。
特撮作品のヒーローや怪物の中に人間が入っているのを知っていたわりには、自分の日常に宇宙人が現れた気になったりとか…。
それから大人になって自分の子どもを寝かしつけようと、例えば『桃太郎』の話をするときなど、創作を加えて話をエスカレートしたりして、それを娘が喜んで聞いていた、といったことがありました。
そういったことを思い出して、企画会議のなかで「子どもに話し聞かせたことが現実になっていく、『不思議の国のアリス』とは逆で夢が現実を侵食するようなファンタジーだったらどうだろう?」と提案したんです。
なので“夢”というよりもむしろ、“ベッドタイム・ストーリー”が本作の根幹になっています。
――夢の世界と現実の世界が度々スイッチしますが、それらのシーンを描くにあたり注意された点は?
夢と現実の世界を描くために、例えば岡山が舞台だから『桃太郎』とか、子どもから見た親の姿や、知っている世界で構成される夢のなかの情景など、本作ではさまざまなギミックやディティールが盛り込まれています。ですが、これらの要素を上映時間内でひとつひとつ説明できないので、観る人がなるべく直感的にわかるようデザインの意味性などに力を注ぎました。
――現実世界の風景と夢の世界が混ざっていく設定は、特撮の影響があるのでは?
僕自身、特撮の影響も強く受けていると思います。1960年代にやっていた『ウルトラセブン』という特撮TVドラマで、モロボシ・ダン(主人公/ウルトラセブン)が畳の部屋で、ちゃぶ台越しにメトロン星人と会話するというシーンがとても衝撃的でした。日常的な景色のなかに非日常的なものが入ってくる怖さに、妙なリアリティを感じたんです。その時期、寝室のふすまの前にメトロン星人が立っている夢を見て、そのことを今でもよく覚えているくらいです。僕はその経験を、意識的に演出として使っているところがありますね。
なるべく見たことがあるところに見たことのないものを入れる。それによって作り手は観ている人に対し、より一層親近感を湧かせることができますし、落差での驚きを作ることもできる。それは、作品作りを始めた当初からずっとやっていることです。
――2020年という“ちょっと未来”が舞台となっていますが、どうやって“ちょっと未来”を作り出したのでしょうか?
最初は現代を舞台にした物語を作ろうと思っていたのですが、誰もがわかりやすいタイミングで東京オリンピックが決まりました。そしてこのオリンピックは、きっとひとつのターニングポイントにもなると思ったので、舞台を“その辺り”に変更しています。
──では舞台を“ちょっと未来”にすることで、どんなテーマを描こうとされたのでしょうか?
以前作った『東のエデン』では“世代の対立”という問題を描き、解決策を模索しました。それはその後も頭に残っていて、今作でも僕のなかで描きたいものの一つとしてあったんです。そこで“世代の対立”の最もミニマムなケースとして家族を選んだわけです。
またそれを顕在化するためには、何をモチーフに描けばいいかと考えた結果、“テクノロジー”というキーワードが出てきました。日本は20世紀に成功を収めたために、21世紀にその成功体験がじゃまをして、そこに世代間の対立、断絶があるように感じています。例えば海外で打ち合わせをするときなど、日本人はいまだシステム手帳に手書きですが、海外の人はみんなラップトップを持って、その場で打って全員で共有し、すぐ次の仕事に入る。日本人だけそこからわざわざ部屋に帰り、議事録を起こし直して…っという。そういったことだけでも日本は遅れていく。そこに見えるのは、古い世代の固定観念に邪魔をされる次世代のジレンマです。そしてそういったことは、もしかしたら家族にも当てはまるんじゃないかなと思ったんです。
劇中では自動運転車が登場します。自動運転の技術は僕らが思っていたよりはるかに早くできましたが、法整備などの面で行き詰っている。それがまた世代の問題でもあると思うんですよね。
3.11を機に、観客も作り手も気分が変わってしまった
――舞台が岡山県の倉敷ですが、なぜ“ちょっと未来”なのに田舎を選んだのでしょうか?
多くの人が、東京で起きていることが日本の中心のような気がしているけれど、東京で起きていることは、日本全体から見ればローカルな部分もある。
例えば、今の日本が抱える地方の過疎化をはじめ、高齢化だったり少子化だったりという問題は、東京にいるときにはあまり具体的には見えてこない。でも田舎に帰ったときに身に染みて実感します。田舎で起きていることのほうが、日本全体として見たらポピュラーなんじゃないかと。
田舎を舞台にすることで今の日本が抱える現実も見えるし、「この日常が永遠に続いたらな」というファンタジーにも見えるんじゃないかと。
――今までの神山監督の作品群とは一線を画す作品だと思いますが、それは一体どのような理由からでしょうか?
これまでの作品で僕が描いてきたのは、SFやハイファンタジーのなかで世界を救うヒーローでした。ですが東日本大震災を機に、作り手も観客も大きく意識が変わってしまったように感じます。
日本は世界から見ればすごく幸せなはずなのに、実感として幸せだと感じている人が少ないように思います。終わらない日常とは、80年代ぐらいから言われてきましたが、いままではそれが長く続き、だからこそ「終わらない日常」が“敵”になったり問題提起となって、それに対峙していくヒーローを描くこともできたんです。
ところが震災を機に、それまで隠れていた格差や不条理などが顕在化した。すると今度は、「永遠に続く平和、終わらない日常」こそが最も得難いファンタジーになってしまった。その大きな変換のなかで、「作品作りもアプローチを変えなければいけない」と強く感じました。
宮崎(駿)監督が『風立ちぬ』を発表したとき、いまの時代の「幸せとはなんだろう?」という問いに「自分が愛した人に、自分を肯定してもらうことこそがいちばんの幸せ」という結論を描かれたことに、強く共感できたんですよ。
そういった自分の想いにフィットするものを作ろうと今回は考え、本作の世界観ができあがっていきました。
――最後にメッセージをお願いします。
新たな、そして一方で僕のこれまでの作品の延長上にある、とてもチャーミングな作品ができあがったと思っています。
主人公・ココネの年代、ココネの親の年代の方はもちろんですが、さらに上の世代に共通する“家族の物語”を描いています。ぜひ、観にきていただけたらと思います。
特筆したいのが、神山監督自身もこだわったというエンドロール部分。高畑充希さん演じる主人公ココネが歌う『デイ・ドリーム・ビリーバー』が切なく甘く、胸に残ります。原曲は1967年にアメリカのアイドルグループ“ザ・モンキーズ”がリリースした『デイドリーム』。それを伝説のロックアーティスト忌野清志郎が日本語の歌詞をつけたのが、本作のエンディングでも歌われる『デイ・ドリーム・ビリーバー』。この日本語歌詞、実は、亡き母への想いを綴ったもの。そんな情報を頭の片隅に観ていただけると、より本作を堪能できると思います!!
(TEXT=春錵かつら)
DATA
ひるね姫~知らないワタシの物語~
ROAD SHOW:3月18日(土)
HP:http://www.hirunehime.jp
Twitter:@hirune_hime
STAFF:
監督=神山健治
脚本=神山健治
演出=堀元宣・河野利幸・黄瀬和哉
キャラクター原案=森川聡子
ハーツデザイン原案=コヤマシゲト
作画監督=佐々木敦子
CAST:
森川ココネ=高畑充希
モリオ=満島真之介
モモタロー=江口洋介
志島一心=高橋英樹
渡辺一郎=古田新太
ジョイ=釘宮理恵
佐渡=高木 渉
森川イクミ=清水理沙
タグ