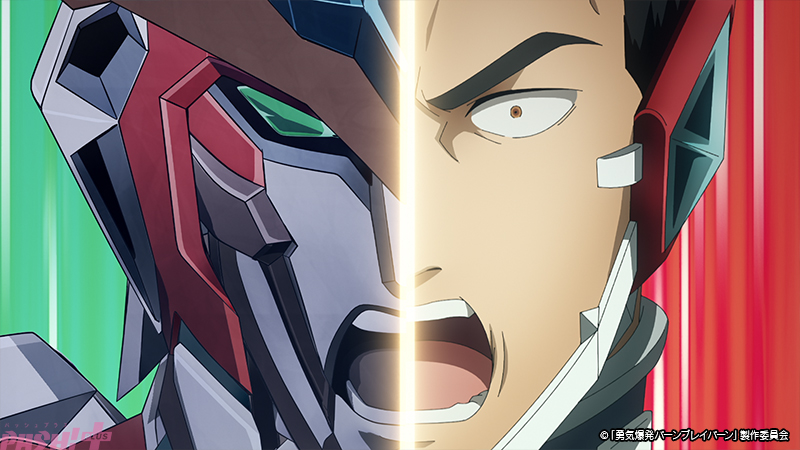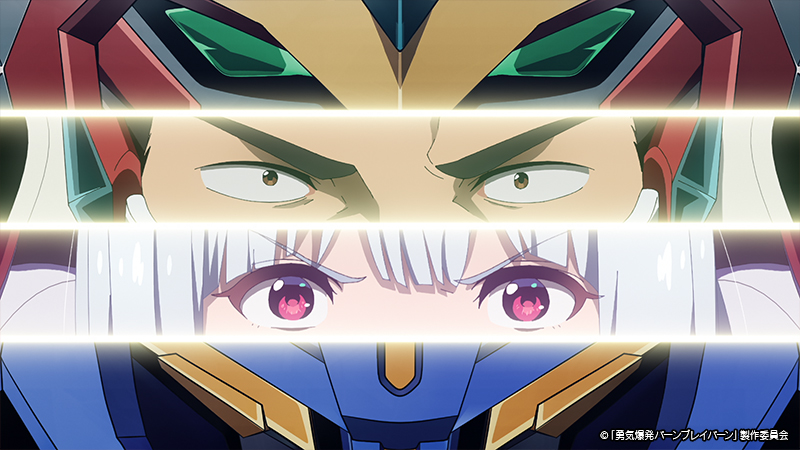interview
平成の名作アニメ『おジャ魔女どれみ』佐藤順一×山田隆司×馬越嘉彦が思い出を振り返るインタビュー!
2019.04.29 <PASH! PLUS>
PASH! PLUS
2019年2月7日で放送開始から20周年を迎え、さまざまな20周年企画が発表されたアニメ『おジャ魔女どれみ』。本作は、1999年2月7日に第1期がスタートした平成の名作アニメのひとつです。
1999年2月7日に第1期がスタートし、2000年には第2期『おジャ魔女どれみ♯』、2001年には第3期『も~っと!おジャ魔女どれみ』、2002年には第4期『おジャ魔女どれみドッカ~ン!』が放送。さらに劇場版やOVA『おジャ魔女どれみナ・イ・ショ』、2011年~2015年には小説『おジャ魔女どれみ16』シリーズなど、さまざまな形態で展開されてきた本シリーズ。
PASH!PLUSでは、20周年という記念すべき節目に合わせて、『おジャ魔女どれみ』を全3回にわたり大特集! 平成の終わりを前に、第1回“思い出コラム”、第2回“スタッフ座談会”、第3回“おジャ魔女キャスト座談会”の3つの記事をチェックしてください♪
第2回スタッフ座談会に出席したのは、1年目(通称、無印)のシリーズディレクター佐藤順一さん、全シリーズでシリーズ構成を担当した山田隆司さん、キャラクターコンセプトデザインの馬越嘉彦さんと、プロデューサーの関 弘美さん! 全4作でシリーズディレクターを担当(共同担当を含む)した五十嵐卓哉さんは、残念ながら都合があいませんでした。20年経って、今だから話せることも含めて、貴重なお話がいっぱい!
今なお愛され、視たことがない人には今からでも視てほしい名作『おジャ魔女どれみ』に注目です!
最初の制作から20年! 当時を振り返る思い出トークに
――まず、20年を迎えた素直な感想からお聞かせください。
佐藤:最近、仕事を一緒にする人から『どれみ』を視てましたって言われることが多く、次女の友達からも『どれみ』がバイブルですって言われて。当時、みんな観ていてくれてたんだって実感できるようになるまで20年かかるんだな、と思いました。
山田:バイブルなんてすごいですね。
佐藤:かなり計算して考えていたのにね。
山田:今やろうと思っても、このメンバーって集められないんじゃないですか。ぼくもちょうどノってるときで、佐藤さんも勢いがある時機で、馬越さんも売れはじめていて、すごいいいタイミングだった気がするんですよね。関さんに集めていただけて、すごくよかったなぁと。時代がぼくらを集めてくれた、みたいなところを感じましたね。やっていて楽しかったし、それが長く続いて卒業式までできたというのは、奇跡に近いんじゃないかなと思います。
馬越:始まりこそいろいろ模索しながらでしたけど、山田さんがおっしゃった通り、きれいに終われたのがほんとに気持ちよかったですね。でも、OVAやライトノベルみたいなものもあって、案外つかず離れず寄り添ってきたので、改めて20周年という感じでもないんです。
――佐藤さんは、しばらく間が空いてますね。
佐藤:そうですね。ほぼ最初のシーズンしかやっていません。企画立ち上げのときにエンジンを全開にした記憶があって、そのときから卒業までいきたいね、というのはありました。それを見込んで立ち上げてはいます。
――最後までいられなかったのは残念ではありませんでしたか?
佐藤:そうでもないんですよ(笑)。後は楽をさせていただきましたが、ずっと作りつづけるのは大変なんです。そのぶん、最初のたいへんなところを頑張りました。
山田:そういう選択もあったということですか。
佐藤:最初にしっかりレールを敷いておかないと後で苦労しますからね。
――立ち上げのとき、山田さんも卒業までと考えていましたか。
山田:2クール、第1シリーズの中盤くらいで延長があるとわかったんです。そのときにそれなら卒業までいきたいなっというのはありましたね。それで、1年1年更新していくわけじゃないですか。それが気持ちよかったですね。
ああ、今年もできる、あと1年つきあえる、みたいな感じがあります。毎年テーマをつくっていたんですよね。最後の年は卒業がテーマだった気がします。ほかに3年目のももちゃんのときがコミュニケーションとか。そういう大きなテーマをちゃんと作って、ほかの脚本家の皆さんもあわせて書いていただいたのが、すごくよかったと思いますよ。
――馬越さんはコンセプトデザインとして最初に呼ばれたときの感触はいかがでしたか。
馬越:関さんや佐藤さんたちが、僕の持っていったものを見ながら、キャラを構築していく作業でした。毎回、なにかしら材料をひねり出して持っていかないといけないんですよ。もう、だんだんネタがなくなっていくのを覚えています。でも、なんかもっていけば、なにかしらアドバイスをもらえたりして形になっていくんです。
山田:クラスメイト全員やったんだからすごいですよ。
関:無印の頃のポスターは馬越さんじゃない人が描いたように見えるんですよね。どれもそのときに馬越さんが描いてるんですけど。だんだん変わっていきました。
山田:あいちゃんはどんどんデコになってく。
馬越:最終的には全員デコになってます(笑)。
佐藤:キャラ表通りに描いたらリテイクですからね。作画は困ってたみたい、去年はOKだったはずなのにって。
馬越:でも4年も続くとは思ってないですから。1年なんとか乗り切ればって、毎年やっていったら4年経っていたんです。
――魔女ガエルには苦労したようですね。
馬越:カエルのようでカエルじゃないんですけど、カエルっていう最初のイメージから離れられなくなっていたんです。あの形は苦しまぎれで描いてあったもので、なにか打ち合わせには持っていかないと―って。
佐藤:基本的なオーダーはこうしてくれ、というものじゃありませんからね。「こうではない」という程度のオーダーしか出せない。
――で、それが気に入られたわけですね。
佐藤:そうですね。紙のすみっこのほうに描いてあった『もうだめ、もうなにも出てこない』みたいなやつ。緑に塗っちゃえばカエルっぽくなるから(笑)。
――最初はもっとカエルよりだったんですか?
馬越:かなり。カエルを一所懸命追求していました。でも、違うな~って。
――クラスメイトも大変でしたね。
佐藤:主役を超えるようなものは作れないし、かといいって面白みがないのもダメだし。
馬越:どうやったか、もう覚えてないですよ。自分の同級生の特徴とか使いながらだったはずですけど。クラスメイトのスチールということでイラストを描いても、あの子がいないとか、人数が合わないとかそういうことがありましたよね。
――山田さんはクラスメイトを作るときのご苦労といえば?
山田:林野くんとかは小学校のときのクラスメイトをそのまま使いましたね、断りもなく(笑)。でも、それ作るために朝から一緒に関さんとか監督とかとみんなでガ~ッと話して。まだ出させるの、みたいな。ぼろぼろになってましたけどね。夜中にピザの注文して。今の働き方改革ではダメなパターン。社員じゃないのに!
佐藤:クラスメイト30人決めて、席順を決めたかったんですよ。ドラマの『金八先生』とかそうなんですよね。席順が決まっていて、いつも同じ子が座ってる。だから、具体的に誰とかわからなくても、その子が出てくるとクラスのあのあたりに座ってる子だなってわかる。それをやりたくて、その他大勢をアニメーターの自由作画にしませんでした。
アニメーターさんの自由にできるエリアとして、いろんなキャラクターを並べたり作画できる楽しみがあるところだとは思うんですけど、それを奪って(笑)。視ている子どもたちがそのクラスに一緒にいるような感じを目指しました。で、実際にやってみたらすごくたいへんだったんですよね(笑)。
山田:スタッフの名前とかも使ってますね。
――関先生は関Pですね。
関:ええ。権力の限りを尽くしました(笑)。最初はもっと実物に近いキャラだったんですけど、もっとかっこよくしてくれとプレッシャーをかけて。そのときの私に近いキャラがおんぷちゃんのお母さんになってましたね。
佐藤:ボツにするのもったいないですから。
山田:自分はいじられるが好きじゃないので、あいちゃんが大阪に行って目撃した、お母さんが抱いてる赤ん坊をタカシくんにしたんです。これでオレの名前使ったからね~って。
佐藤:関さんは、小学校中学校、幼稚園のときの記憶がすごいんですよ。あの子はねえって話を聴くだけで40分くらい。ぼくは小学校の頃のこととか忘れてるんで。
関:でも、私の記憶を引き出してくれたのが佐藤監督だったんですよ。小学生の頃の文具メーカーのプレゼントグッズの話を佐藤監督がしたんですけど、私は佐藤監督が名古屋という都会育ちだからあった話であって、私の田舎にはなかったと言い切ったんです。でも妹が覚えていました。
近所の子から妹がもらったグッズを、私が取り上げてどっか失くしちゃったそう。なくされたほうは覚えてるんですよね。それがきっかけで記憶が出てきやすくなりました。
佐藤:こういうことがあったってドラマで覚えてるからですね。
関:グッズを妹にくれたのが近所に住んでたアキラくんとケンちゃんで、男の子だから青とか緑が欲しかったのに、届いたのがピンクだかオレンジだかで女の子っぽい色だったからくれたらしいんです。その話からアキラくんとかケンちゃんのことを思い出したわけ。
山田:男はすぐ忘れちゃうよね。ぼくは卒業アルバムを持っていったんだけど、全然おぼえてない。
関:卒業アルバムを開いて、名前を隠して思い出せるかやってみるわけです。そうすると、本名を思い出せなくてもあだ名とかは思い出せたりするんですよ。
――特に感情移入したキャラはだれでしょうか。
佐藤:主人公のどれみはある意味ステレオタイプで、なんにでも首を突っ込んで内面的には友達思いで子どもたちにいちばん好かれやすいタイプなので、共感よりも一番動かしやすいキャラクターでした。ドラマとして一番想い出に残ってるのは矢田くんかな。好きでトランペット吹いてて、でも小学生だから『きらきらぼし』でいいなって。
関:今開催中のショップでクラスメイトの人気投票をしているんです。中間結果でのトップは矢田君です。二番目が意外にも玉木麗香と小竹が争ってます。これは東京でも大阪でも同じです。
山田:作る側の愛情が反映されてますね。ホントは玉木っていい子なんだよねって。思い出すと美化されるような脚本を書いたんです。個人的に高飛車な子って好きなんですよ。でも、ただ高飛車じゃダメじゃないですか。どうして高飛車になったか、父親との関係みたいなものとかを描いておかないと。
佐藤:自分の気持ちに素直だったんですよね。
山田:だから自分を飾っていない。そういえば、玉木がカメラっ子の島倉のことを親友だと思っていたら、向こうはそうでもなかったとか。彼女もいろいろありながら、それぞれにうまくやっていくみたいなことがありましたね。
――そうすると、山田さんの思い入れのキャラというと、やはり玉木ですか?
山田:玉木にも思い入れはあるんですけど、やはりあいちゃんかな。いちばん脚本を書いたので、すごく幸せになってほしいなと思ってます。密かに感じてましたけど、クラスの子ってけっこうお金持ちが多いじゃないですか。あいちゃんみたいな子もいていいのかなって。
――馬越さんの思い入れがあるキャラクターは。
馬越:クラスメイトだったら信秋くんかな。五十嵐さんの演出回でした。信秋くんの投票での順位が気になりますね。投票には直接いかないといけないんですか? はづきが壊れるのが恒例になってきてる頃でしたね。
山田:無印の話で誘拐されたとき、崩れたような気がするな。はづきちゃんは笑いのツボのズレ具合も面白かった。あ、ここで笑うんだ、みたいな。
――クラスメイトが多くて収録も大変だったのでは。
佐藤:キャストを全員決めたはいいけど、スケジュールを押さえているのに、毎週出番があるわけじゃないという問題が発生してしまいました。レギュラーなのに20話くらい出ないとか。
関:どれみのオーディションには、いろんな声優プロダクションが大挙して送り込んできましたよね。ひとつのプロダクションが20人くらい。すでに有名になってる声優と売り出し中の若手をセットにしてるような感じでした。
佐藤:『どれみ』の頃はナチュラル系の声優さんが人気だったので、そういう声優さんがオーディション参加者に多かったんですよ。でも、それだとどれみの声が中学生か高校生くらいに聞こえちゃいます。
それに、スーパーやデパートのゲームコーナーにあるジャンケンゲームとかで「じゃ~んけ~んぽ~ん」って声が流れたときに、通り掛かった子がどれみだって思ってくれないといけません。ナチュラル系の声は弱いんですよ。ぼっぷ役のオーディションに来た人がみんなどれみ候補になって、どれみ役のオーディションに来た子が残らない感じでしたね。
――はづきちゃんの秋谷さんは初々しかったですね。
佐藤:秋谷さんはアフレコ経験がまだ少ない頃だったんですが、オーディションのときにキャラがたっていたんですよ。
山田:第1話や第2話のゆっくりなテンポが最後のほうはぜんぜん違うなあ、と感じました。
佐藤:だいたい1年やると変わりますね。最初は物語と絵が作られてるところに、声をあてています。キャストがキャラクターにあわせているんですが、1年経つとお互いにわかってくるので、キャストの演技に作り手があわせてくる。この子はこういう個性がおもしろいからこう動かそう、とか。そうなってくるとキャラクターとキャストが一体になって、演技も幅が広がっていく。
――馬越さんは声を聞いて感じたことはありましたか。
馬越:宮原さんはおもしろいと思いましたね。矢田くんで出ていたのが、ももこで新しい声を聞かせてくれて。独特の持ち味に引っ張られてくみたいなところもありましたよね。
――もっとも大切にしていたことはなんでしょう。
佐藤:たとえばあいちゃんの家庭問題に関しても、ぼくからは発信していなくて、山田さんから今回やっていくぞ、という姿勢を感じていたんですよね。山田さんとは『夢のクレヨン王国』でも組んでいて、ドラマ部分に関しては間違いないと。『どれみ』を始めるにあたって考えていたのは、低年齢層に向けて見てもらうのはそうなんだけど、もう少し上7~9歳に届けるにはどうすればいいかな、ということでした。
やっぱりドラマであったりが大事かな、と『どれみ』ではそれを押さえていきたいし、そこは心配がない。逆にぼくが思ったのは、そっちに重きを置くとだんだん話がシリアスになって、マジメになっていってしまいます。それを戻す作業をぼくがしっかりやろうかな、と。
3歳から6歳の子のモチベーションはいいお話ではなく、やっぱり楽しかったかどうかなので、バカバカしいこととかくだらないことをちゃんと保証していこうと思ってました。そこを最初に重点的に考えたんです。
関:魔法のポロンをリモコンみたいにってアイディアは佐藤さんだったよね。
佐藤:魔法ものを始めるといっても、魔法で大人になります、アイドルになります、みたいな限定的な魔法と、『魔法使いサリー』みたいになんでもできる魔法があって、どちらをやるかを考えたんです。今考えたら違うかもしれませんが、このときはなんでもできる魔法かなと思っていたんです。
なにかおもしろいアイディアはないかなと思っていたら、小さい子が飼っていたカブトムシが動かなくなっちゃったけど「電池どこにいれるの」ってお母さんに聞いたというニュースを見かけて。
そこから、子どもたちはなにか動く、作用するときに電池を入れるということを自然にわかっているんだと。だったら電池に相当するものを入れると魔法が使えるのは、自然に受け入れられるのかなと思ったんです。それがお話を作りにくいオールマイティー魔法にあたってのアイディアとしていいな、と。それが魔法玉になりました。
山田:使って減るのがいいよね。どれみはお調子者だから無駄遣いしちゃうの。ステーキ出して、もっと厚いやつとかね。
佐藤:でもステーキは食べさせない。
山田:それが大事。
佐藤:ドドはすごく食べる。
山田:最後まで食へさせなかった。ライトノベルでも食べてない。運命なんだ。うちの娘も、ごちそうというとステーキなんですよ。一回食べさせたのがいけなかったんですけどね。なにかあると、父さん、ステーキだよねって。
佐藤:今の時代だとまたちょっと違うんじゃないですかね。
――山田さんが大切にしていたのは?
山田:やっぱり他人を傷つけることが一番きついかなと思ったので、そういうことがないようになるべくやった気がします。ぼくは感情のまま書いているので、直しが出るときもそういうところが多かったような気がします。でも、やはり知らないうちに傷つけちゃうことってありますもんね。
あと、それぞれのキャラクターの成長をちゃんと計算しながらできたと思います。月に一回構成会議をやっていて、そのときに脚本家の個性に合うエピソードを振り分けるんです。ホントはおれがやりたかったのになぁとか思いながら、別の脚本家にこれを書いてください、というのもよくありましたね。
――ライトノベルはご自身ですべて書けましたね。
山田:ええ。関さんと、次はこんな感じで、みたいな話をしながら進めたんです。でも、それでみんなスーパーになりすぎちゃったなぁと思いましたね(笑)。反省として。あのどれみがここまで成長していいのかな、とね。どれみはどれみなんだから、そんなには変わらないだろう。教師に向いてることも途中まで自分でわからなかったし。まあ、痛みがわかる子だから、教師はあってますよね。
――馬越さんが大切にしていたことは?
馬越:ホントに絵のことだけなので、それぞれの“らしさ”みたいなものを出そうと思ってやっていたと思いますね。はづきならこう、あいこならこう、というのを4年やったので、途中からはもう自然とできるようになっていたと思うんですけど。勝手に動いてくれるというか。だから次はどんなギャグ顔にしようか、探り探りやっていたのがおもしろかったですね。
山田:脚本もそうでしたね。頭の中で勝手に動き出すという感じでした。最初に動き出せば、あとはそれを写していくだけ、みたいになりましたもの。最近はそういう作品が少なくなったなぁ。それだけ愛情とかが注がれていたのかな。
――どれみのくずし顔は1話からすごかったですよね。
馬越:あれは完全に佐藤さんの絵です。それがすごく勉強になりました。
佐藤:7話くらいまではラフ原画のチェックをしていました。崩し顔とか、アニメーターさんによってはちょっと生理的にかわいくないことってあるんですよ。どんなに崩しても最終的にどこかちょっとかわいい感じが残ってることが重要です。
どちらかというとシリアスなギャグシーンとかありますし。そんななかでギャグのバリエーションを考えて、ああでもないこうでもないとやっていた記憶があります。
山田:すごいなぁと思ったのが第1話の水飲み場のどれみの泣き顔。あっちから撮るって、あんなの始めてみた。どれみがへんな顔でさあ。
佐藤:どれみにとってはたいへんシリアスなのに視聴者には愉快なシーンです。
山田:あれはすごいなと思ったなぁ。あのシーン、どれみにとってはちょーシリアスですよ。それがああなった。
佐藤:そのバランスがギャグ顔とか崩しの重要なところです。シリアスなシーンというのはお話が伝わるけど、子供たちがキャラを好きになるのは圧倒的に崩しのときなんですよね。それは、誰かのために一所懸命やっていて、そのときにドジって崩し顔になったとき、笑いながらその子が好きになるというのが大事だと思います。
――子どもがまねしやすい絵ですよね。
馬越:最初に言われましたもんね。描きやすいようにって。
佐藤:子どもがキャラの特徴を描けば、そう見えるようなデザインにしてくださいとお願いしました。最初に描いたキャラには手足にリアルな立体感がありましたけど、棒みたいにしてくださいって指示も出しました。
アニメーターさんの中にはリアルだと描けないって人もいるんで、誰が描いても元気いっぱいになるようにお願いしますって。関節をちゃんと描けばちゃんとかっこいいポーズになるんですけど、描けない場合も多いから最初から関節ないようにしておけばいいかな、と。
馬越:オーディションのときには斜に構えた絵を持っていったんですよ。しゃらくさいですよね~。
佐藤:描けるのはわかってるんです。でも、ここでは描けない人の気持ちになってみないといけない。
山田:アニメーター改革だったんですね。
馬越:最初はとまどったんですけど、絵を描くカロリーを減らすことになるのでテレビシリーズ50本をやっていくのに役立ちました。それに形のとりかたや影のつけかたも変わってきます。あそこまで続くとやり方として正解だったな、と。
スタッフ陣の心に残るエピソードは?
――お気に入りのエピソードをお願いします。
関:私が憶えているのは山田シナリオ佐藤演出で、シナリオのアイディアが影山さんから出ていたという母の日の話
山田:中山しおりちゃんの話ね。あれ、木漏れ日の演出がすごいよかった。
佐藤:関先生が片親って理由で先生の面接を落とされたりしていて、やってて手応えのある回でありました。絵コンテに関してはちょっと襟を正して。担当したのはわりとバカバカしい話が多いと思うんです。
自分にとって印象に残っているのは、やっぱり第1話かな。たとえば、どれみが魔法を使うシーンに歌をいれたい、と思っていたんです。あの曲はもともと主題歌として作っていたものを挿入歌にしたんですよね。『マジンガーZ』が出動するときと同じようにやりたい、と。
実際にやって、思った通り印象的にできたのが第1話のわけです。思っていた楽しさとか、それによっていろんな気持ちが出てきて正解だったなと感じたんです。
山田:ぼくは『♯』から、映画の続きのピアノが春風家にくる話ですね。実は病気をした父にあの回を見せたら、すごく感動してくれたことがあるんですよ。映画の続きをやりたいというのは、五十嵐さんがずっといってたんです。どれみがなぜピアノをやめたのかをちゃんと描きたかったんですよ。そのトラウマをとり払うことができる話にしようと、ちょっと大人っぽい話でしたけど、すごく好きですね。
あと『ナ・イ・ショ』の12話。今はちょっとつらくて見れない。あれはずっと心にひっかかるものがありますね。佐藤さんの涙を流させないで泣かせる演出が秀逸ですよ。
佐藤:作る方にはけっこうつらい話ですね。
――馬越さんはいかがですか?
馬越:やはりピアノの回ですかね。どれみのお父さんお母さんの芝居がすごくて、楽しかったです。ああいうさりげない優しさを表現する芝居を描くことはあまりなかったので、アニメーターとして楽しかったですね。
――ご自身が手がけなかったエピソードではいかがでしょか。
山田:ガザマドンが好きなんですよ。男の子っぽいじゃないですか、あれって。ぼくには書けない。
佐藤:ぼくは岡(佳広)さんの演出が好きなんですよ。あいちゃん話が多いせいか、なんだか日本映画のエッセンスが感じられます。子ども向けアニメなのに。
山田:わかるわかる。
関:クラスメイトて小説書いてる横川信子の話も。
山田:よく書いてるよな、小説。あと、彼女のうそついてるときのあひる口とかおもしろいなと。
――馬越さんは?
馬越:長峯くん演出の、プロレスのむつみの回もなんとなく好きです。
――個人的には、登校拒否の長門さんの話が衝撃的でした。
山田:うちの娘の担任の先生にも『どれみ』を観てもらっていて、不登校の子の話をやりたいんですけど、どうなんですかねって聞いてみたんです。一回だけで解決するような問題じゃありませんよ、たいへんなんですよ、とのお返事でした。その前に取材で聞いていたので、何回かに分けてやろうとは思っていたんですけどね。
ただ、ほんとに学校に近づくだけで嘔吐しちゃうといった描写など、ちゃんと取材できてよかったと思いますね。やはり3回に分けてやってよかったかな。長門さんの場合みたいに、友達を知らないうちに傷つけちゃうってあるからね。
傷つけたほうは忘れるけど、傷つけられたほうはずっと憶えてるみたいなこと。今だったら書けない、当時だから書けたような気がしますね。よくやらせてもらえましたね。それもあって『どれみ』がオリジナル(アニメ)でよかったと思います。あの頃はなにをやっても大丈夫みたいな気がしてましたもの。
――帰国子女のももちゃんも、当初教室では英語だけというのが驚きでした。
山田:日本語字幕なしというのは正解でしたよね。字幕がないおかげで、視ている子どもたちが入り込めたと思います。字幕があったらドン引きですもん。当時は、ああいう帰国子女もだんだん増えてきていました。
この少し前に川崎市で取材したことがあって、クラスの中に親が離婚してる人や帰国子女がどれくらいいるかとかを文部省の人とも話をしたりしてありました。それなりに正確で時代にあってると思ってました。
「またこのメンバーでなにか作りたい」
――ラストでどれみが魔女にならないというのはどなたのアイディアですか。
山田:みんなですよ、みんな。ホントは魔女にならせたかった気持ちもあるんですけど、でもこの子たちは魔法がなくてもちゃんとできるように成長してるよねって。だから「魔女にならない」という決断をさせました。
――とはいえスタッフの決断も難しかったのではありませんか。
山田:そうですね。でも彼女たちはそれぞれが成長してるから、たぶん魔女にならないという結論になるんだろうなぁと思いました。
――佐藤さんはそれを知ったとき、どう思いましたか。
佐藤:ぼくは魔法から卒業するんだな、とそんなに違和感はなかったですね。もともと日常話が多いし、どれみの魔法がなくても成立する話がけっこうあるんです。基本的には子どもたちのドラマですから。
見ていた子たちの立場になると、彼女たちには魔法がないわけです。その子たちが『どれみ』を見て育っていくとき、ささいな魔法がなくってもやっていけるのがいいかな、と思ってるんです。
――物語は綺麗に完結していますが、やってみたいことはおありでしょうか。
佐藤:やり残したことはありませんね。2.5次元舞台は…おもしろいかも。
馬越:フラット4出しますか。
山田:オーディションでイケメン揃えて。でも、あそこもしょぼい国だよね(笑)。それがよかったのか、ぼくたちには。これですごい王国だったらいやですよね。
――キャストのみなさんに聞いてみたいことはありますか?
佐藤:つらかったことはないですか(笑)? いつまでも帰してもらえなかったとか。
山田:でも彼女たちにとっても出世作っぽいものになってますからね。ぼくは…今と当時でアニメに対する思いは変わってますか?。
佐藤:千葉さんや宍戸さんがショップに行ってるみたいですね。今だからできるようになった楽しみで、よかったと思います。ぼくらは当時、子どもたちの反響よりも、視聴率とか玩具の売り上げとかの数字を相手にしていたんです。子どもたちが番組をどれだけ面白がってくれたかは、全然わかんなかったんですよ。それが今はああいうショップで感じられますからね。
山田:でも、あの頃の子どもたち、女の子たちの心になにかのタネを植えたみたいになっていて、そのまま伝わってるなと。
――馬越さんは聞いてみたいことはありますか?
馬越:『おジャ魔女』やってよかったですかって?
佐藤:そんなの怖くて聞けない。
――ご自身にとって『どれみ』とは? 最後に、ファンの方へメッセージもお願いします。
馬越:ここまで付き合いの長い作品になって、寄り添ってきたキャラクターたちは特別でもあるんですが、自然にそこにいる存在にもなっています。すっかり自分の手に馴染んでいるものではありますが、20年経って、またなにかしら新しいものを出せたら楽しいなと思っています。
山田:『どれみ』を書いてるときが、たぶん仕事が一番充実しているときだったと思うんですよ。ちょうど『こち亀』やって、『おじゃる丸』立ち上げて、『犬夜叉』も始まって、そんな時期に『どれみ』ができたのがすごい。いろいろあるなかでも、やっぱりオリジナル作品を、しかも東映アニメーションでできたのは自分にとってすごい幸せだったと思います。
オリジナルの強さもわかってるし、弱さも当然知ってますけど、その中で4年間やり切ったのは自分の中でも最高の宝物みたいな感じです。だから自分の代表作はと聞かれたら、必ず3本の中には『どれみ』が入ると自信をもって言えます。そういう作品なので、みなさんも忘れずに語り継いでください。
佐藤:『どれみ』のときも『セーラームーン』や『クレヨン王国』でも、女児に向けて自分の中にあるものを投入していた当時は、子どもの反応がすぐにわかりませんでした。それがどれだけ正しかったのか、こうすればよかった、みたいなものがだんだん見えてきたのが20年経った今ですね。子どもたちが番組を観るとき、当時はわからなきゃいけないこと、わからなくていいことの判断が難しかったんです。
例えば言葉の意味がわからなくても、うれしい、幸せ、楽しいということがわかればいいんですよね。わからなきゃいけないレベルを探り探りやってみると、そんなにわからないことを気にしなくてもいいってことが最近わかってきたんです。
子どもたちって、わからないことの方が多いので、わからないことはそんなにストレスになっていないんです。そんなことより楽しかった感覚、うれしかったとか悲しかったとか、そういうことのほうが気になるんだってわかってきました。それを次の作品に活かせる財産ができたのがうれしいですね。
ちょうど『どれみ』を見ていてくださっていた方が成人されて、社会人になったりお母さん、お父さんになったりしています。そういう人たちも、これからのターゲットとして我々は考えることがあるのかな。それも含めていろいろできたらいいなと思ってますし、またこのメンバーでなにか作りたいと思っています。それが実際にできたら、応援していただければありがたいです。
――ありがとうございました!
DATA
■『おジャ魔女どれみ』
『おジャ魔女どれみ』20周年記念公式サイト:http://www.doremi-anniv.com/
『おジャ魔女どれみ』20周年記念公式Twitter:@Doremi_staff
©東映アニメーション
タグ